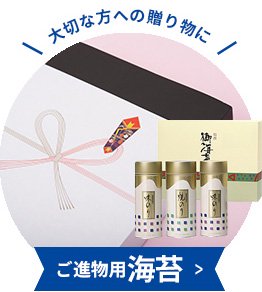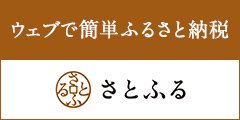江戸時代以降の海苔の歴史
海苔は大昔から日本人に親しまれてきました歴史がありますが浅草海苔が生まれたのは江戸時代になってからのことです。 浅草海苔の名前の由来は様々な説があり定かではないのですが、江戸城を徳川家康が築いてからは浅草が隅田川の河口にある使い勝手の良い港として江戸に送られてくる物資を輸送していた場所になりました。そして浅草にある浅草寺は昔から由緒がある、お寺で徳川家が祈願をしている、お寺でもあったために江戸の町人の間でも人気が高く門前市ができるほどの盛況だったので東京湾で採られた海苔が浅草で売られて良い評判を得たことが由来となっていると考えられます。 後になってから浅草紙を作るときの紙すきの方法の真似をしてできた抄き海苔が享保の時代に考案されて浅草海苔として今現在の乾海苔の様式が日本全国に広まったという歴史があったのです。 江戸時代の浅草では隅田川の当時の清らかな水を使って紙すきが頻繁に行われていたため海苔を抄く行為は紙すきをヒントにして考案されたものになります。 明治時代の頃になると日本に西洋人がやってくるようになり海苔を食べている日本人を見た西洋人は黒い紙を食べていると勘違いし驚く人がたくさんいました。 養殖の本格的な歴史が始まったのはイギリス人の女性の学者が第2次世界大戦の後すぐに海苔が生殖するメカニズムを解明して人工的に種付けをする技術が開発されてからになります。日本ではアサクサノリという品種が主流でしたが今現在養殖されている品種は、およそ8割がスサビノリという品種です。
海苔の豆知識一覧へ戻る